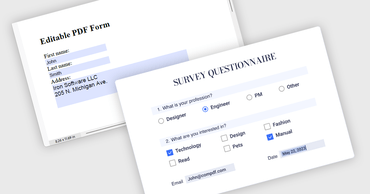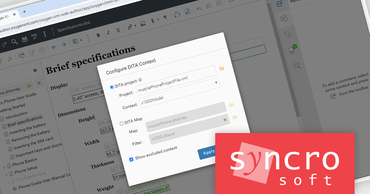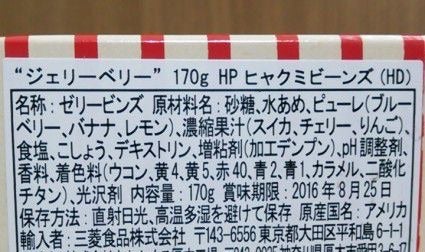『ハマータウンの野郎ども』
Learning to Labour
ポール・E・ウィリス著/熊沢誠・山田潤訳
ちくま学芸文庫 1996年刊(単行本は85年刊)
ついこの間まで、勉強しすぎだと言われた日本の子どもたちは、最近の国際比較調査によれば、いまでは他の先進国の子どもと比べ、ほとんど勉強しない部類に入る。勉強することに関心を持たず、早くから勉強から「降りてしまう」子どもが増えている傾向を示す調査結果もある。さらにいえば、私の研究でも、勉強から「降りる」ことや基礎学力、さらには自分たちで調べたり発表したりする学習への取り組みが、生まれ育つ家庭環境と関係していることがわかっている。教育の世界で、恵まれた家庭の子どもと、恵まれない子どもとの「二極化」が進行しているのである。
子どもたちばかりか、若者たちも厳しい現実に直面している。正社員ではなく、フリーターや派遣社員などの非正規の職に就く若者たちは、二百十万人以上になるといわれ、仕事にも就かず学校にも行かない「ニート」と呼ばれる若者の数も、五十万人とも六十万人ともいわれる。やりたい仕事が見つからない、自分に本当に合う職業がわからない、といった若者自身の意識の問題もあるにはあるが、ここにも明らかに家庭環境の影響がにじんでいる。恵まれない家庭出身の若者のほうがフリーターや無業者になる可能性が高いのである。
さらに若者たちの間で所得格差が拡大していることを示す統計もある。安定した職に就けないと、生涯賃金が五千万円にしかならないという推計もある(正社員なら高卒でも二億円になる)。
厳しい競争社会の到来と併せて、家庭環境の影響を受けながら、勝ち組と負け組との差がはっきり現れる「格差社会」に日本が突入した。そういう警鐘も鳴らされている。
駆け足で紹介したが、こういう日本の現状と近未来像を念頭におくと、今回取り上げる本の凄味が見えてくる。翻訳書のタイトル『ハマータウンの野郎ども』だけだと、多くの人は教育の本とは思わないかもしれない。だが、イギリスで一九七七年に原著が出版されて以来、本書は英語圏を中心に、教育の社会学的な研究書として、大学の授業の講読リストに必ずといってよいほど登場する文献の一つであり、この分野の現代の「古典」といって間違いない。
原題は、“Learning to Labour”。直訳すれば、「労働への学び」となるのだろう。だが、英語の原義には、「学習から労働へ」とか「労働力(者)になることを学ぶ」といった意味を匂わせる、複雑な含みをもったタイトルである。
この英文タイトルから想像できるように、本書の中心テーマは、労働階級出身の少年たちが、どうして自分もまた父親たちのように労働階級へと自ら進んでなっていくのかを解き明かすことにある。
社会学者の著者ポール・ウィリスは、イギリスの古い工業都市バーミンガム近郊の町、ハマータウン(仮名)の中等学校に通う少年たち(英語ではladsと呼ばれる「野郎ども」)の生活を、フィールドワークの方法を用いて丹念に追い、彼らの日常を活写していく。
ケンカやいたずら、悪ふざけといった腕力が象徴する男らしさの価値。酒、たばこ、パブへの出入り、そして性体験といった大人ぶった振る舞い。労働階級の大人の男たちの文化に通じる行動を同世代のまじめな少年たちよりもいち早く身につけること、教師に逆らい、校則にも法律にも触れる悪さを繰り広げることが、野郎どもの楽しみである。と同時に、それが彼らの成熟の証にもなる。学校に順応的な生徒たちより、自分たちの方がずっと大人であり、すぐれていると思えるのも、若者たちの行動が労働階級の文化に通じ、それに支えられているからだ。
その同じ階級文化にあと押しされて、野郎どもは、まじめに机に向かい勉強することを、女々しいことだと卑下する。そして、その延長線上で、ペンと紙を使うホワイトカラーの仕事を自ら忌避するようになる。それとは反対に、身体と力を使う手労働を男らしさの発露として価値あるものと見なす。こうした階級に根ざした考え方と学校への反抗とがスムーズにつながっているところに、野郎どもが教育という上昇移動の手段を自ら遠ざけ、親たちと同じ労働階級の仕事へと進んで就いていく仕組みがはたらいている。等価交換の方程式の中で、週払いの賃金しかもらえない肉体労働の担い手へと自らを位置づけていく学びの過程がここにあるのだ。こうしてウィリスは、野郎どもの日常を克明に記録し、聞き取り調査を重ねることで、自由な意志に基づいて、労働階級が自らを再生産していく様を明らかにする。
「オレたちとヤツら」――イギリスには、階級の明確な違いを区別する有名な表現がある。一九七〇年代のイギリスには、こうした階級対立と、それを背景にした労働階級の若者たちの学校への反抗と拒絶が存在した。本書の優れた点は、こうした階級文化のはたらきを明らかにしたに留まらず、野郎どもの鋭い目差しを通して、学校が纏うさまざまな神秘主義のからくりを暴きだしたことにある。
たとえば、労働階級の勉強嫌いの少年たちにとって、少しばかり努力したところで、その見返りに得られる職業の機会には大差がないこと。そうした生徒たちが身につけるべきとされるのは、知識や優れた成績などではなく、学校に逆らわないまじめな態度そのものであること。生徒の興味や関心を尊重したり、彼らの生活に直接関係する学習を提供しようとする子ども中心の進歩主義教育も、こうした教育のまやかしをとり繕うものにすぎないこと。教育のタテマエ論に惑わされることなく、野郎どもは学校の真相をまんまと見抜き、教師たちの裏をかく。その様を描き出すことで、ウィリスは、現代社会において学校がはたそうとする「錬金術」のからくりを読者の前に示すのである。
学校は全ての子どもを社会的成功に導く機関ではない。必ず誰かが敗者の烙印を押され、社会の底辺に押しやられる。それを見抜いてしまう労働階級の少年たちの鋭い洞察と同時に、それゆえの皮肉な結末――自ら学校に反抗することで、上昇移動の機会を閉ざしてしまう逆説――を生み出す学校のからくりを暴くのである。
「階級」という言葉がほとんど死語となっている今の日本にとって、ウィリスが描き出した野郎どもと学校の関係は、はたして遠い世界の話なのだろうか。冒頭に紹介した最近のいくつかの傾向を重ね合わせていくと、むしろ、堅固な労働階級の文化を欠いた日本で、教育の格差が拡大していくことの問題点が浮かび上がる。
階級文化という集団的な支えがないことは、若者たちが進路選択の問題を含めさまざまな問題を自己責任として引き受けなければならないことを意味する。そこで底辺へと追いやられる日本の若者も、自ら進んでフリーターやニートの道を選んでいるかのように見える。ところが、学校から「降りる」ことで、将来の成功の道を自ら閉ざしたとしても、それを称賛し、支持してくれる野郎どものような階級文化は日本には存在しないのである。
おそらく、集団的な反抗の基盤を欠くこととも関係しているのだろうが、権威への反抗や反発が行動として外に表れるよりも、対人関係や「心」の問題として内向しやすくなる点にも日本の若者の問題の特徴が表れているのだろう。ニート(NEET、Not in Education, Employment, or Training)という、本来は雇用上の立場を示すにすぎないイギリス生まれの専門用語が、日本ではいつの間にか「引きこもり」までを含む意味を帯びて使われるようになった。ここに象徴的に示されているように、日本の若者たちの困難さの一因は、個人個人がバラバラにされ、社会性を欠くことと関係しているように思えてならない。
さらにいえば、男らしさや性的早熟を誇りとする階級文化の欠如は、問題を抱える日本の若者たちの成熟への拒否という形を纏っているようにも見える。早く大人になろうとして階級の再生産に乗ってしまうのではなく、大人になることの拒絶が社会の格差拡大とつながる。イギリスとは正反対の関係が浮かび上がってくるのである。
こういう写し鏡の役割を果たし、他国での問題発見に寄与してくれるところに、本書の優れた研究たるゆえんがあるのだろう。読むたびに新しい発見をもたらしてくれる、教育の社会学的研究の「古典」である。
Kariya Takehiko●東京大学大学院教育学研究科教授。1955年東京生れ。米ノースウェスタン大学にて博士号(社会学)取得。ノースウェスタン大学客員講師などを経て現職。『教育の世紀』(弘文堂)、『知的複眼思考法』(講談社)など著書多数。現在、英オックスフォード大学セント・アントニーズ・カレッジに客員研究員として在籍。2005年サントリー学芸賞「思想・歴史部門」受賞。